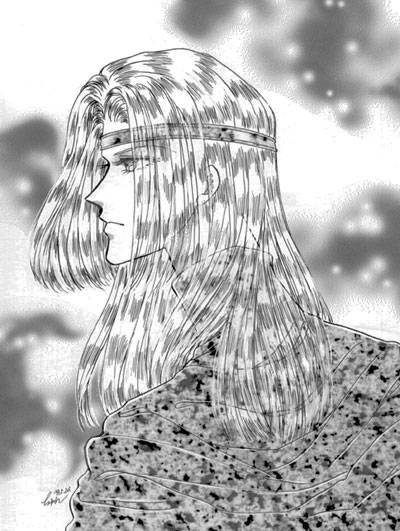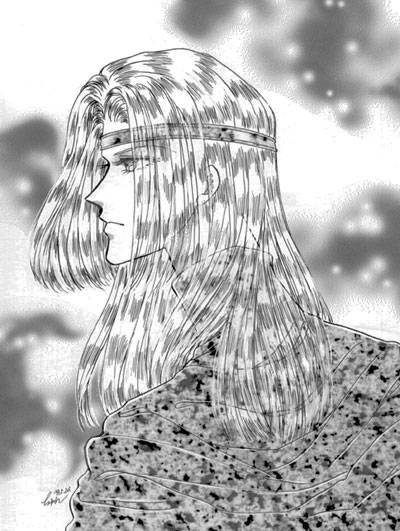|
予定より、だいぶ遅れてしまった。
それが、新米妖獣ハンターの少女アディスの、偽らぬ本音だった。護衛を引き受けゲルバから脱出したのは、まだ雪が降り積もる季節の事である。だが護衛の対象である少年、ローレン・ロー・ファウランと共に門をくぐった彼女の眼に映るカディラの都は、既に夏の盛りを迎えようとしていた。
本来ならここへは、春になる前に到着するはずだったのだ。自分とローレンと、雇い主のルノアード・ロー・ファウランの三人で。けれど現実には、辿り着いたのは今で、雇い主だった青年はいない。
「……アディス?」
かぼそい声で呼ばれ、アディスは慌てて振り返る。現在彼女達がいるのは、都の門から少し離れた通りだった。石畳で舗装された道路は、荷車に野菜を積んで市場へ向かう人間や、今日の食い扶持を稼ごうと足早に進む人々でごった返している。ぼんやり突っ立っていて良い場所ではなかった。
「ごめーん。いきなり賑やかなトコに来たから、ちょっとぼんやりしちゃった。具合悪くない? ローレン」
そばかす顔の少女に尋ねられ、ローレン・ロー・ファウランは微かに笑みを浮かべて首を振る。親代わりに自分の側にいてくれた義理の叔父、ルノゥことルノアードがゲルバ国王に捕われ拷問を受けている夢を見たその時から、具合が悪くない日など一日たりともなかったが、己を本気で心配し親身に面倒をみてくれる相手に、そんな事実を正直に告げる気にはなれない。
「平気、大丈夫だよ。それより早く城へ向かった方が良くないかな? 歩きで行くとなると、ここからじゃ結構時間がかかりそうだよ」
「そうねぇ。二時間ぐらいはかかるかしらね」
アディスは頷き、彼方に小さく見える大公の居城へ眼をやって溜め息をついた。二人がカディラの都を囲む壁の門前に到着したのは昨日の夜の事だったが、余り遅い時間帯に城に着くのはまずいだろうと開門を求めず、一旦近くの村まで戻り野宿したのである。
アディスとしては、体が弱っているローレンの為にも食事付の宿に泊まりたかったのだが、残念ながら先立つものがなかった。なにしろ雇われた時に貰った金は、ゲルバを脱出する際妖獣から襲われ逃げ惑っている内に財布ごと落としたらしく、手許にない。
その後世話になったヤンデンベールの城塞を去る時点で、守護職のエルセイン子爵から都までの旅費にと渡された虎の子の金も、途中通り抜けようとした街の市場で引ったくりにあい失ってしまったのである。
こんな事なら遠慮せずザドゥ隊長の提案を受け入れて、護衛兼道案内の兵士を付けてもらうんだったわと悔いても既に遅く、それから後カザレントの首都を目指す二人の旅は、馬車を使えぬ為徒歩で宿にも泊まれぬ辛いものとなった。
幸い、財布を盗まれた時にはもうカディラの都までそう遠くない距離に来ていた為、野宿生活は三日で済んだが、朝から晩まで歩き詰めなのにお金がないのでパンも買えない、食堂にも入れないというのは、育ち盛りの二人にとってきつかった。
川辺でのんびり釣りをする暇もない為魚も得られず、やむなく道路脇に生えている木の実草の実で飢えを凌ごうとしたものの、それら僅かばかりの食料は彼女達の空腹を紛らわす役には立たなかった。
それでも元々健康体で、しかも妖獣ハンターであるアディスは、この状況下でもさほど体力を消耗する事はなかったが、普通の人間で以前から体が弱っていたローレンの方はそうはいかない。心配する少女の手前、必死で元気そうに振る舞ってはいたが、実際には野宿一日目からバテ気味だった。
そして都に入った今は、いつ力尽きて倒れるかわからぬ程危なっかしい足取りである。だからここはあたしが頑張らないと、とアディスは気合いを入れ直す。いざとなったらローレンを背負って城まで歩く覚悟を決め、彼女は勇ましく大公の居城に向けての一歩を踏み出した。
カザレント現大公ロドレフ・ローグ・カディラが四月の下旬に妻であるイシェラ出身の王女セーニャ妃によって暗殺されかかってからというもの、次期大公と目される嫡子クオレル・トバス・カディラ(本名ライア・ラーグ・カディラ)は多くの義務と責任を負わされ、多忙の日々を送っていた。
彼女が背負い込んだ責任と、仕事の半分を分担してくれていい存在は一応いる。だが宰相ディアルが産んだ異母兄ルドレフ・ルーグ・カディラは、クオレルが跡継ぎとして周囲に紹介されていた頃、生死も定かでなかった。
ゲルバ支配下地域のイシェラよりどうにか生還、帰郷を果たした後は、公子として次期大公と臣下達の間に立ち双方の意思の疎通をスムーズにさせる潤滑油となり、職務の重圧に嘆くクオレルの愚痴の聞き役にもなってくれたが、己の出生上の疑惑を気にしてか公式な席には姿を見せようとしなかった。
結果、各地から訪れた人々と謁見するのは大公の嫡子としてお披露目済みなクオレルの業務となり、都人の代表者から陳情を聞くのもクオレルで、行政官と議論を交わすのもやはりクオレル、主立った臣下が出席する会議の場に出て断を下すのもクオレルと、全てクオレル一人の役目になっていた。
クオレル自身は、以前侍従として父である大公の側近くに仕えていた為、大公の仕事がどういうものかはある程度理解していた。が、それにしても少し忙しすぎやしないかと、連日彼女は思う。
真面目にやろう、誠実に対応しようとすればするだけ、眼を通さねばならない書類とそれに関連した調べ物の数は増え、接見しなければならない人々や、足を向けねばならぬ場所、直に見て歩かねばならない地域も増える一方なのだ。
要するに君主というのは、一人で政治家と役人の長と軍の最高司令官と裁判官を兼ねており、加えて商才もなければ勤まらない職務なのである。しかもこの職業は、ほぼ親から子へ受け継がれるのだ。本人の才能や資質ではなく、血縁関係で決められてしまう。自分は向いていないとか、不適格だとか言ったところで、嫡子が一人しかいなくては選択の自由はない。
大公ロドレフ・ローグ・カディラの場合もそうだった。好色で自堕落な前大公ケベルスの所業により、庶子の兄弟姉妹は一山いくらで量り売りにできる程(その中にはロドレフの母の実家より遥かに血統の良い、有力貴族や大臣の娘が産んだ子も多く含まれて)いたが、正妃の産んだ子は彼ただ一人。それ故、ケベルス亡き後大公の座に就くのは彼しかなかった。しかし、その一方で彼は、いつでも取り替えのきく存在と見做されていたのである。
ロドレフがすんなり大公の地位を与えられたのは、カザレントという国の体面上の問題であった。唯一の嫡子たる人間が君主の地位を受け継ぐのは当然と、国民も周辺諸国も納得する、言わばその為の通過儀式。裏を返せば、先に嫡子が一度でもその座に就いた後ならば、兄弟姉妹の誰か、自分達にとってもっとも都合の良い存在と首をすげ替えるのも可能、と思われていたのだ。
就任直後ロドレフの大公の地位は、周囲の思惑や駆け引き次第という非常に不安定なものだった。
そして当のロドレフ自身は、大公の地位など大して望んではいなかった。だが、望んでいないからといって国や民への義務を投げ出し知らぬ顔を決め込む程、無責任な男にもなれなかった。何より、軽蔑していた父親の不始末や散財の尻拭いは、やらねばならぬ立場にあった。
だから彼は、就任するなり国庫の破綻を回避すべく、前大公が手を付け税金を流用して贅沢をさせていた女性達の処分と財産の没収を決めたのである。同時に、後日の憂いを取り払うべく異母兄弟姉妹の大量殺人を行って、血の大公などというありがたくない通り名をもらう羽目になったのだ。前大公の元で暴利を貪っていた連中に思い知らせる為の行動で。
妻からも怖れられ、殆ど孤立した状態で戦い続けたロドレフが宰相ディアルを求め必要とした気持ちは、今のクオレルにはよくわかった。一人で頑張るには無理がありすぎる、と。
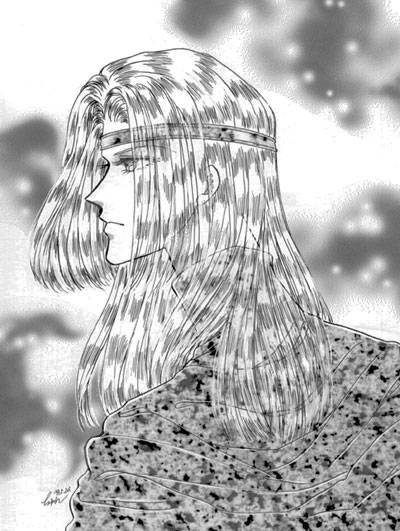 それにしても、と書類への署名の手を休め、銀髪の大公代理は溜め息を漏らす。
「後を継いだらもう最後、一日中職務に拘束され年中無休のフル稼働営業で、刃傷沙汰や暗殺のおまけ付き、しかも死ぬまでそれが続く。君主の座になど、頼まれたって座るもんじゃない、か……。大公がしょっちゅうぼやいていたのも納得できるな。こうも超過勤務が当たり前の過重労働では、私の胃に未だ穴があいてないというのは奇跡に近いぞ」
「はっ?」
午後の仕事に必要な書類を受け取りに来た文官が、扉を背にしたところで代理君主のボソボソとした呟きを耳にし反応する。何でもない、と断言したクオレルは、署名済みの書類を手渡すと仕草で部下の退出を促した。
訝しげな表情の文官は、空耳だろうかと首を傾げながら執務室を去る。飲み物を運んできた小姓も下がらせ一人になると、クオレルはストレス解消に遠慮なく机を叩き出した。木材を使った頑丈な机である。女の拳で百や二百、叩いたところでびくともしない。
だいたい何で、と髪を乱し彼女は喚く。
「何で書類に眼を通すのが私一人でなければいけないんだ? 許可だの認定だのの署名を記すのが大公の正式な跡継ぎでなければ駄目だなんて、誰が決めた! 兄上も兄上だっ、血筋がどうだろうと宰相の地位に就けば、書類の決裁や役人との面談はできる。だのに毎日毎日何かと理由を付けては逃げ回って……」
宰相なんて私の柄じゃない、と本人は言うが柄じゃないからと逃げられるなら、自分だってとっくに逃げている。次期大公なんて器じゃない、自分は補佐する立場にあるのが精一杯だ、と。それが許されないからこうして踏み留まっているのではないか。自分以外に誰も、大公の嫡子にはなってくれないのだから。
「……まぁ、兄上の場合見た目がああだから、嫌がる気持ちもわからないではないけれど……」
ひとしきり喚き散らした後で、肩の力を抜いたクオレルは実感をこめ呟く。異母兄ルドレフ・ルーグ・カディラの外見は、事前に情報を得ていない者が見れば二十代半ばとは絶対に見破れない、と断言できるものだった。
どれ程上に見積もっても、せいぜい十八かそこら。大公就任三十周年を祝う式典の時に現われた彼の外見年令は、誰が見てもそんなものだった。そして二年が過ぎた今も、何故か十八以上に見るのは難しい容姿なのである。おまけにルドレフの場合、他にも問題があった。
たとえ真実十八歳だとしても、普通は大人扱いを受ける。クオレルもそうだった。十七前後辺りから、周囲の者は彼女を一人前の大人と見做し信頼して接するようになった。中には大公に優遇されている生意気な青二才、などとやっかんで嫌味を言う輩もいたが。ともかく、実際に年が十八だとしても、役職に就いて悪い年齢ではないのである。
が、もしもルドレフが宰相に就任し地方の行政官と接見した場合……、相手がどう思うかは予測がついた。こんな子供と何を話せと言うのかと、怒鳴り込んでくる様までが想像できる。
「兄上の童顔ばかりはなぁ……。本人に責任がある訳ではないけれど」
いや、あの性格も原因の一つかもしれない。そう考え、クオレルは嘆息を漏らす。だからこの際開き直って堂々と公子として表に出てほしいのだが、それを言うとルドレフは引く。思いっ切り引く。フラグロプのしでかした一件、放った言葉の毒は、今なお棘の鎖となってルドレフの心を縛っているらしかった。
「ああもうっ! 何で大公はあの男を解任しておいてくれなかったんだ? おかげで私は余計な苦労を背負い込むハメになったじゃないか!」
解毒剤がまだ作れないイシェラ産の毒により、現在も仮死状態のまま寝台に横たわる父親にまで文句をつけ、クオレルは拳を山積みの書類へと振り下ろす。そこへ新たな文官が顔を出し、おずおずと告げた。ゲルバ出身だという妖獣ハンターの少女と連れの少年が先程門前に訪れ、次期大公様にと書簡を門番へ渡したそうです、と。
文官が差し出したのは、薄汚れた一通の封書だった。
封筒の表に書かれた文字は、雨にでも濡れたのか滲み掠れて満足に判読できない。しかし裏はそうでもなかった。そこに、馴染みある人物の署名を眼にしたクオレルは、既に門番の兵士が一旦開封し検分した手紙を取り出して、書かれた内容を確認する。
「どうやらヤンデンベールから、例の招かざる客が来たようだ。予定では一昨日の朝到着するはずだったが」
一読した大公代理は、整った顔に皮肉な笑みを浮かべ文官に命じる。行って門番にその二人を城内へ引き入れるよう伝えよ、そして湯浴みと軽い食事を与えた後、少年の方だけ謁見の間に通すようにと。
「そこで皆に引き合わすとしよう。ユドルフ・カディラが実の叔母と作った子、ゲルバへ嫁いだイシェラ王女に産ませた息子とやらをな」
声が冷ややかになったのは、何も溜まったストレスだけが原因ではない。ユドルフ・ユーグ・カディラ。それはカザレントの住民にとって断じて忘れられぬ憎むべき者の名、唾棄すべき存在を意味する名前であった。
前大公ケベルスが、公子だった頃のロドレフの妻に手を出して産ませた子供。セーニャ妃が産んだが故に、名目上はロドレフの息子となっている人間。
クオレルにとっては同腹の兄。父親は異なるが、兄弟にあたる者だった。
異母兄であるルドレフの事は、愛しい肉親として認めているクオレルだが、ユドルフに関しては態度が異なる。
いったい誰が自国の滅亡を願った男を、父親の暗殺を何度も目論んだ人間を愛しむだろうか。クオレル自身は直接的な被害をこうむった訳ではなかったが、カザレントの国民の中には、ユドルフに故郷を焼き払われた者や家族を虐殺された者もいる。親戚や知人が殺された者となれば、かなりの数になるだろう。
そんな男が残した不義の子に、好意的になれるはずもなかった。そうした負の感情は、決してクオレル一人が持つものではない。ローレン・ロー・ファウランは招かれざる客だった。彼の責任ではなかったが、それでも招かれざる客なのだ。
(……なんか、綺麗だけど冷たい眼をした人ね)
強引に対面の席まで同行したアディスは、初めて間近に見た銀髪の大公代理に対し、そんな第一印象を抱く。
一方、ユドルフ・カディラの存在を嫌悪しその息子と会う事に不快感を拭いきれなかったクオレルも、己の命令を無視してでしゃばった少女に、優しい視線を向ける気にはなれなかった。
「私がここで会う約束をしたのはユドルフの息子一人なはずなんだが、いつのまに分裂したのかな? しかも性別が異なるように見受けられるが」
氷の微笑を浮かべての言葉に、アディスの頬が紅潮する。隣に立つローレンは、無言のまま面を上げていた。
「お言葉を返すようですが、ローレン・ロー・ファウランは分裂などしていません。あたしがこの場にいるのは、それが依頼された任務だからです」
「任務?」
「はい。あたしは今年の三月ゲルバにて、ローレンの叔父であるルノアード・ロー・ファウラン様と契約を交わしました。残念ながら雇い主の彼は途中で妖獣の牙にかかり、その後行方知れずとなって生死も定かではありませんが、契約は有効です」
高い地位にある、異国の偉そうな大人達に囲まれながら、アディスは一歩も引かなかった。無礼者と罵るなら罵ればいいんだわと、全身でローレンを庇い立つ。
「あたしが交わした契約は、ローレンを守りこの都まで無事送り届ける事、でした」
クオレルは眉を寄せ不思議そうに呟く。それなら契約は終了したのではないか? と。 既にローレンはこうして大公の居城に着いている。この上何を以て任務は継続中だと主張するのか。
アディスは、昂ぶった気を静めようと深呼吸を繰り返し応えを返す。
「契約は、まだ有効です。ローレンを守るという点においては」
ルノゥが彼女を雇った時点では、ここカディラの都、大公の居城にはセーニャ妃とイシェラ国王ヘイゲルがいた。ユドルフの生みの親と、ローレンの母方の祖父が。それは即ちローレンにとって、身内と呼べる存在がいたという事だ。
「あたしを雇ったファウラン公爵の弟君は、そこへローレンを託せば大丈夫だと信じていたんです。でも、現在先のお二方はこの城におりません。ローレンの居場所はもうないかもしれない、そんな状態で契約終了と離れる事はできません!
あたしを雇い、任せてくれた方の為にも、見極めたいと思います。ここに彼を置いて去ってもいいのかどうかを」
「……なるほど」
微かに笑みを浮かべ、クオレルは頷いて見せる。
「その意気込みには敬意を表するが、実際に彼の居場所がないとわかった場合はどうするつもりか? 勇ましいお嬢さん」
「えっ?」
虚を衝かれ、アディスは返す言葉を失う。まさかそんな台詞を言われるとは、考えてもいなかったのだ。
「この城に、彼の身内は既にいない。全くその通りだ。正確に言えば、そこにいる少年は母方から見れば私の甥に、父方から見れば現大公の甥にあたるが、あいにくユドルフのような男の息子を甥と認める気など、私にも大公にも全くない。そもそもユドルフ・カディラを大公家の一員と認めたい者など、カザレントの民の中には一人もいないはずだ」
「………」
「さぁ、これで君が守ってきた相手に居場所がない事は判明した。それで君はどうするのだ? ハンターのお嬢さん。ご立派な意見を皆の前で述べた以上、おめおめと引き下がったりはしないだろう?」
怒りに赤くなったアディスは、次に青ざめ、震える手でローレンの腕を掴んだ。
「行きましょ、ローレン。こんなとこ、わざわざ来たりするんじゃなかったわ! あたしいっぱい働くから。働いてあんた一人ぐらい養ってみせるから、一緒に行こうっ! いる必要ないわよ、カザレントになんか」
「アディス」
無言だった少年は、ここに至ってようやく口を開く。
「落ち着いて、アディス。からかわれてるんだよ」
「からかわれていようと何だろうと、もう我慢できるもんですかっ! って……何、何の話? からかわれ?」
「カザレントの次期大公様は、いい性格の持ち主だから言葉をそのまま鵜呑みにして受け取るなって、ハンターのお兄さんが言ってたじゃない。忘れたの?」
「あ、うん……。そう言えばそうだったわね。でも……」
穏やかに指摘され、思い出したアディスは同意する。しかし反論も忘れない。それにしたって、ここまでいい性格とは普通思わないわよ、と。
「ヤンデンベールのハンターが、私を何と評したと?」
興味深げにクオレルは訊く。それまでの態度が嘘のような真剣な眼差しに、アディスは驚き、壁際に立ち並んだ臣下一同はざわめいた。
そうした周囲の反応など、クオレルはさして気にしなかった。手招きでローレンを近くに呼び寄せ、返答を促す。ゲルバから亡命してきた少年は、臆する事なく次期大公に近付き、視線を合わせて対峙した。
「別に評したと言う程の事はありません。ただ、あのハンターのお兄さんは僕に言ったんです。カディラの都に住む銀髪の綺麗な次期大公は、昔からいい性格の持ち主だった。簡単にやり込められてベソをかくなよと。今にして思えば、彼なりに心構えを説いてくれたようです」
「ほう」
パピネスらしい物言いだと納得しつつも、恋しい相手からいい性格の持ち主と断言されたクオレルは、嬉しさ半分悲しさ半分と、何とも複雑な心境になって苦笑する。
「それで僕は考えたんです。もし本当に貴方がハンターのお兄さんの言った通りの性格なら、僕がこの城に留まる理由は得られるかもしれないって」
「ローレン?」
いったい何を言いだすのか、とアディスは戸惑う。しかし、ローレンは顔色こそ悪いものの、冷静だった。決して自棄を起こしこんな事を言い出した訳ではなかった。
「常時罵詈雑言の受け手になる人間を一人、お求めになる気はありませんか? 次期大公様」
微笑んで、ローレン・ロー・ファウランは尋ねる。
「幸い僕は、ユドルフ・カディラの血を引いているだけで充分この国では憎悪や罵倒の対象となり得るようですから、存分に毒舌を奮えると思いますが、いかがでしょう。買っていただけますか? 次期大公様」
ゲルバからの亡命者が口にしたとんでもない申し出に、謁見の間は騒然となった。室内で唯一椅子に腰かけていたクオレルは、これが座っての対面で良かったとしみじみ思う。もし立ったままで相対していたら、自分は腰を抜かしていたかもしれないと。
とはいえ、クオレルの表情は心と裏腹にさほど変化していなかった。故に周囲の誰も、彼女の内心の動揺には気付かない。最も近くにいたローレンさえも。
「面白い提案だな。己を身売りすると言うのか」
「はい」
「やめてったら、ローレンっ!」
何を言ってるのよと叫ぶアディスを無視し、クオレルは値段の交渉に入る。
「それで、いくらで私に売るつもりだ? 仮にも公爵家の息子として育ったなら、そんなに安くはないだろう?」
「そうですね……」
ローレンはチラリとアディスに眼を向け、ニッコリ笑顔で言葉を返す。
「彼女が一ヶ月ぐらいは暮らすに困らない額を、と言ったら望みすぎですか? でも、僕が決めた値段はそれです。それだけの金額を、アディスに渡してほしいんです」
「ローレンっ!」
「全額、妖獣ハンターの彼女にか」
「はい。それに見合うだけの働きを、アディスは今日までしてくれましたから」
「ふむ……」
「やめてって言ってるでしょっ! ローレン。今すぐこの馬鹿げた提案を取り下げてちょうだいっ!」
詰め寄るアディスに、ローレンは首を振る。
「アディス、僕はこの国に入ってから最近までずっと、具合が悪くて殆ど寝たきりの日々を送っていたよ。だから、考える時間だけは嫌になる程あったんだ。これはその上で出した結論だよ。撤回するつもりはない」
「ローレン?」
「ルノゥが渡したお金が君の手許に残っていたなら、僕もこんな考えは持たなかったろうけど。でもあのお金はないんだろう? 君はずっとただ働きで僕を守ってた。それじゃ嫌なんだよ。僕は僕の得たお金で、君に報酬を支払いたいんだ。これまでの感謝をこめて」
クオレルは椅子から立ち上がり、二人の会話を中断させる。別室で正式な金額交渉をしようとの誘いに、ローレンは承諾して従い、アディスは激怒憤慨した。
「駄目よ、ローレンっ! そんなお金欲しくないわよ、あたしはっ。受け取ったら許さないんだから!」
嵐のように騒ぎ立てるアディスを連れて、次期大公とゲルバからの亡命者はその場を退出する。後に残された臣下一同は、今後を憂いて溜め息を漏らすのみだった。
* * *
実行したら絶対嫌がる、と異界の魔物は腕の中の相手を見おろし思う。さっきまで辛うじて意識があった青年は、受けた傷が元で現在は昏睡状態に陥っていた。
意識を取り戻させる為には、新たな衝撃や苦痛を与えねばならない。けれど苦痛を与えるという事は、また一歩相手を死に近付ける事にもなった。
既に基礎となる体力を失った身体は、生死に関わる傷を負った際の自動治癒もできない状態になっている。血は流れるままだったし、傷口は時間が経過しても塞がらない。失った手足も、甦りはしなかった。
瞼を閉ざした青年の血の気のない頬を撫で、異界の魔物は暫し躊躇う。死なれるのは嫌だった。されど自分に名を与え、呼んでくれた相手が消滅するのも嫌だった。
もうこれ以上傷つけたくない、苦痛を味わせたくはないと思う。しかし、そうしなければルーディックは消えるという現実が目の前にあった。同時に新たな傷を負わせた場合、生命そのものが失われる可能性も。どっちにしろ失うしかないのかと、異界の魔物は歯噛みし、こんな選択肢のない運命を負わせた存在を呪う。
いくらこれがルーディックの身体でないからといって、ルーディックを消して良いはずはない。記憶を奪っていい訳はないのだ。だのにあの王はそれをした。レアールの魂が死んだと伝えた瞬間から、ルーディックがルーディックとして生きていた頃の記憶を消しにかかった。今後レアールとして生きねばならない者に、人間のルーディックの記憶は不要だと。だが、不要とされた記憶を、人格を消される側の恐怖を妖魔の王はわかっているだろうか。
確かなはずの己の記憶が消滅する。家族の顔が、名前が思い出せなくなる。故郷が記憶から消え、教育係として過ごした日々の記憶も次々と欠落し……。
最後にルーディックに残ったルーディックとしての記憶は、苦痛を伴った悪夢に近い。ガーラムが強制し続けた行為故に、それが残ったのは皮肉な結果と言えた。一番忘れたい辛い記憶だけが、ルーディックの中に最後まで残ったのだ。育てたケアスの肉体を乗っ取った蜘蛛使いに死ぬまで痛めつけられ嬲られた記憶、それだけが。
ガーラムにしてみれば不本意もいいところだった。ルーディックが他者に意識を向け、その間自分をないがしろにした、それに腹を立てて暴力を奮った結果、最も嫌いな妖魔の記憶を最後まで残させてしまったというのは。
だがそれも今は、どうでもいいと思えた。
『あの王の思い通りにさせるのも、お前を奴に渡すのもどちらも嫌だ。死なすのも嫌だし消えられるのも嫌だ』
だからこうするしかないと、血で汚れた肌に舌を這わせ、異界の魔物は決意を固める。意識があったら嫌がって喚くなと思いつつ、ガーラムはルーディックの内に潜り込み、捕らえた魂を喰らうべく牙を突き立てた。
|